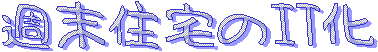
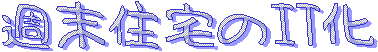
![]() はじめに
はじめに
週末住宅をIT化するには、まずインターネットの常時接続環境が大前提になります。
やはり、山の中なので、常時接続できる環境にあるのかどうかが心配でした。幸い、うちの辺りは、ADSL
8Mのサービスエリアで、しかも局からの距離がそれほど遠くも無く(それでも3km程度あります。)ADSLが対応可能でした。
那須でも、場所によっては様々な制約でADSLが引けない場所もあるようです。これはNTT東日本に問い合わせてみるより他はありません。
![]() ネットワークカメラ
ネットワークカメラ
まず、IT化の要に持ってきたのが、Panasonicのネットワークカメラです。これらは、サーバーの機能を具備しており、PCが無くても遠隔から撮影画像を見ることができます。また、FTPによって指定のサーバに画像を送ったり、メールで配信したりすることも、可能です。さらにI/O端子を持っており、これを使えばE-CON端子を持つ家電製品などをインターネットから制御することも、可能になります。Coregaのカメラは、安価です。画質は劣るし、動かすこともできませんが、定点撮影用には丁度良いと思います。これもサーバー機能を具備していて、FTP転送、メール配信などができます。I/O端子はありません
。
現在の那須 の撮影に使っているのはこのCoregaのカメラです。
![]() Panasonic BB-HCM381
Panasonic BB-HCM381  −−−
屋内用パン&チルト&光学21倍ズーム
−−−
屋内用パン&チルト&光学21倍ズーム
![]() Panasonic
BB-HCM331
Panasonic
BB-HCM331  −−−
屋外用パン&チルト
−−−
屋外用パン&チルト
![]() Corega CG-WLNC11MN
Corega CG-WLNC11MN  −−−
屋内用 無線LAN対応 固定カメラ
−−−
屋内用 無線LAN対応 固定カメラ
![]() 暖房の遠隔制御
暖房の遠隔制御
インターネット経由からの暖房オンは、上記のPanaのネットワークカメラのI/O端子を用いてい
ます。ボイラに一番近いネットワークカメラのI/O端子から(写真1)、パネルヒーター用の石油ボイラー(長府のDBF-1700)
(写真2)のE-CON端子
(写真3)に配線し、インターネットからネットワークカメラを通じてOn/Offすることが可能になりました。
※I/O端子へのリンクはマニュアルのバージョンが上がると切れてしまいます。その際には、ここから新しいバージョンのドキュメントを探してください。
ただし、PanaのネットワークカメラのI/O端子は、本来Panaのカメラに内蔵された12vの電源を利用したオープンコレクタ回路(要は、リレーでなくトランジスタでOn/Offが行われている。)で作られていますが、E-CON端子には既に12Vが出ていたので、これをそのまま利用しています。もしかすると、これは仕様外の使い方になるかもしれません。
また、 実際のOn/Offの動作確認には、室内のネットワークカメラ BB-HCM381を用いています。パネルヒータのパイプに秋月電子で購入したセンサ付温度計を設置して(写真4)、それをネットワークカメラ を通じて目視して温度の上昇・下降を確認するのです。パイプにセンサを直接触れさせているので、すぐに反応してくれます。
中々、言葉で説明するのは難しいですね。興味をもたれたり、ご質問などありましたら、どうぞご遠慮なく週末リゾート生活掲示板に書き込んでくださいませ。